Kは日に日に顔色が悪くなっていった。それは誰がみても明らかだった。顔はこけ、全体的に青白くなり、無精髭をはやし、さらに私が声をかけても何かにおびえているかのように「はい!」と返事をする。
明らかに入社当初と雰囲気が違う。私は心配になりKを飲みに誘った。しかし、決めた日の当日夜になるとKは決まって急な仕事が入ってしまう。何度も何度も調整をするのだが一向に話がまとまらなかった。
Kのことは気になっていたものの、私も仕事に追われ、どうすることもできずにいた。諸般の事情により社内でKに話しかけることはできなかったし、Kもあまり人と関わりを持ちたくないようだった。とにかく自分のことでいっぱいいっぱいの表情をしており、私はどうすることもできず、ただ気に留めることしか出来なかった。
私は私で、諏訪の同行で毎日忙しい日々を過ごしていた。午後を中心に相変わらずの鳴り止まない電話。そしてその対応。案件は様々でそれぞれのクライアントの要求はかなり高かった。後になってわかるのだが、重箱をつつくような要求を諏訪はのんでしまっており、クライアントからの要求がどんどん高くなるという負のスパイラルに陥ってしまっていた。
そして、私はこの時、少し恐怖におびえていた。何故なら、諏訪はあと少ししたらブラック企業を辞めることになっていたからだ。それは諏訪のクライアントをそのまま私が引き継ぐことを意味していた。
つまりあとしばらくすると、この鳴り止まない電話は私が代わることになる。要求が高くヒートアップした、言うなればお祭り状態のクライアントをそのまま私が引き継ぐ形になる。しかも諏訪はクライアントの対応に追われており私とコミュニケーションをとる余裕さえない。つまり、きちんとした引き継ぎが行える状況ではない。
扱っている商材も多岐に渡り、とても諏訪が辞めるまでに把握することはできる状況ではない。質問をする時間も与えられず、ただ単に諏訪の横に座り、同行をするだけの毎日。この時私は、仕事をしていると言う感覚がまったくなかった。
社内のシステムにしても、非常に難解かつ複雑なものだった。さらに特別研修がある訳でもないのでシステムさえ使いこなすことが出来ず、またそれを引き継ぐ時間さえないこの現状。質問をしても返事が返ってこず、また途中でクライアントからの横やりの電話が入るため、なかなか思うように運ばない毎日。仕事上の意思の伝達や疎通がまったくおこなえていない。私と諏訪は明らかにコミュニケーションが不足していた。そのため、次第に私はイライラを隠すことができなくなっていった。
しかし、そうはいうものの、その時の私はなんとかなるだろうとそう思っていた。私は自分の能力に対して一定の自負を持っていたし私ならできるという自信が私にはあった。
しかしその自信は、この後音もなく崩れさって行く。
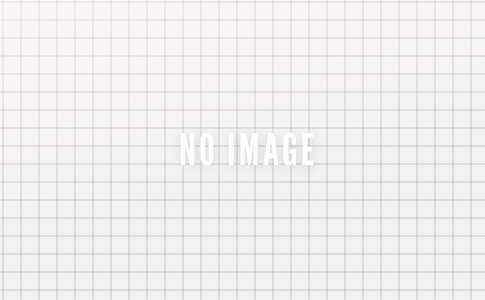
[…] […]
[…] […]